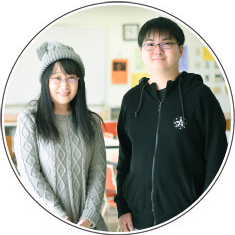患者さんと
ご家族へのインタビュー
〜血友病と生きる
私たちのいろんな気持ち〜
本記事は、血友病について実際の患者さんの体験談を紹介しています。特定の患者さんの体験を紹介したものであり、典型的な患者さんの体験を紹介するものではありません。気になる症状や医学的な懸念がある場合、また、適切な診断と治療を受けるためには医療機関を受診ください。
INTERVIEW
行動して経験し、学ぶことから
自分の可能性が見つかる

インタビュー会場に出向いてくださった桜井さん。仕事や患者会の活動で全国各地を訪れているそうです

桜井佑輔さん
宮城県在住
会社員

1997年生まれ。鉄骨の設計・製造などを手がける企業で、建築物に使われる鉄骨の設計を担当。
「コンピュータを使って鉄骨を設計する仕事でデスクワークが多くなりがちですが、外に出かけるのが好きなので建築現場などにも積極的に足を運んでいます」と話す桜井さん。幼少期から動き回ることが大好きで、今もさまざまなスポーツに挑戦していると言います。これまでの歩みやリスクとの向き合い方などについてお話をうかがいました。
生後8か月で血友病と診断。
小学校1年生から足首のけがが増えた
小学校1年生から足首のけがが増えた
生後6か月のとき、足に覚えのないあざが見つかりました。近くの小児科を受診し、様子を見ることになりましたが、その2か月後にはまた足に血腫ができ、血液の精密検査を受けたところ、血友病Aの重症と診断されました。
歩き始めた1歳の頃には転んだはずみで口元の腱を切り、縫合してもらったものの、出血が1週間止まらないということもありました。
歩き始めた1歳の頃には転んだはずみで口元の腱を切り、縫合してもらったものの、出血が1週間止まらないということもありました。

歩き始めた1歳頃の写真。
この少し前に血友病と診断されました
この少し前に血友病と診断されました
小学校1年生のときに、歩いていて段差を踏みはずし、ひねって右足首を骨折。そこから足首のけがをしやすくなってしまいました。血友病の患者は、けがが連続すると関節症のリスクが高くなるんですね。とはいえ、小学校低学年といえば活発な年代ですから、サッカーやドッジボールをしたり、友だちと遊び回ったりしていました。その結果、右足首にけがが集中し、4年生あたりからはひねってもいないのに運動しただけで足首が腫れるようになりました。
血友病の薬剤の投与もしていましたが、そのほかに足首のケアに役立ったのはアイシングやサポーターです。冷やすと良いという情報を母が患者会で聞いて、小さな保冷バッグを買い、冷却剤を入れて持たせてくれました。サポーターの中に入れられる冷却剤があるのですが、それを教えてくれたのは看護師さんです。その看護師さんも患者会に参加したり、ときには宮城県から東京へ行って勉強会に参加したりして、僕をサポートしてくれました。今も何かあると、その看護師さんと連絡を取り合っています。
血友病の薬剤の投与もしていましたが、そのほかに足首のケアに役立ったのはアイシングやサポーターです。冷やすと良いという情報を母が患者会で聞いて、小さな保冷バッグを買い、冷却剤を入れて持たせてくれました。サポーターの中に入れられる冷却剤があるのですが、それを教えてくれたのは看護師さんです。その看護師さんも患者会に参加したり、ときには宮城県から東京へ行って勉強会に参加したりして、僕をサポートしてくれました。今も何かあると、その看護師さんと連絡を取り合っています。
小学校2年生で病気を自覚。
みんなと対等でいたい気持ちから体を鍛えた
みんなと対等でいたい気持ちから体を鍛えた
自分の病気を理解したのは、小学校2年生のときです。先ほどお話ししたように、けがをして病院に行く機会が増えていました。松葉杖をついたり、包帯や湿布をしていたり。そこで担任の先生と親が相談し、先生からクラス全員に僕の病気について伝えようということになったのです。「桜井くんはけがをしやすい体質なので、過激な運動などに巻き込まないようにしてね」と。
クラスで話をする前に、先生と親から「今度みんなに話すけど、そのときに教室にいる? それとも保健室にいる?」と尋ねられ、僕は保健室にいることにしました。これが、自分の病気を初めて実感した出来事でした。
実はその頃、けがが多くてあまり動けないことから太ってしまい、体型をからかわれたりいじめられたりしていたのです。「学校に行きたくない」と思い、登校しても保健室で過ごしたりしていました。
ひきこもったり内気な性格になったりしそうな状況だったかもしれませんが、僕は「なぜそんなことを言われなくてはならないのか」と考えました。みんなと対等でいたい、みんなと遊びたい、という気持ちだったと思います。
では、いじめられないためにはどうすればいいか。ちょうどその頃、人気お笑い芸人の影響もあって「筋肉ブーム」だったんですね。筋肉をつければ人気者になれるし、もしいじめられても負けないと思えるようになるだろうと考えました。そこで、父が建築関係の仕事をしていて日頃から筋トレをしていたので、僕も一緒に筋トレをしました。体に負荷がかかり、けがをすることもありましたが、筋肉をつけることによって関節が支えられるという意味で理にかなっていたと思います。
クラスで話をする前に、先生と親から「今度みんなに話すけど、そのときに教室にいる? それとも保健室にいる?」と尋ねられ、僕は保健室にいることにしました。これが、自分の病気を初めて実感した出来事でした。
実はその頃、けがが多くてあまり動けないことから太ってしまい、体型をからかわれたりいじめられたりしていたのです。「学校に行きたくない」と思い、登校しても保健室で過ごしたりしていました。
ひきこもったり内気な性格になったりしそうな状況だったかもしれませんが、僕は「なぜそんなことを言われなくてはならないのか」と考えました。みんなと対等でいたい、みんなと遊びたい、という気持ちだったと思います。
では、いじめられないためにはどうすればいいか。ちょうどその頃、人気お笑い芸人の影響もあって「筋肉ブーム」だったんですね。筋肉をつければ人気者になれるし、もしいじめられても負けないと思えるようになるだろうと考えました。そこで、父が建築関係の仕事をしていて日頃から筋トレをしていたので、僕も一緒に筋トレをしました。体に負荷がかかり、けがをすることもありましたが、筋肉をつけることによって関節が支えられるという意味で理にかなっていたと思います。

「とにかく体を動かして遊んだり運動したりするのが大好きだったんです」と語る桜井さん

高校1年生になるタイミングで手術をしたものの、
その後、高校の運動会では、
クラスで足の速い6人のうちの1人として
「ベストメンバーリレー」に出場
その後、高校の運動会では、
クラスで足の速い6人のうちの1人として
「ベストメンバーリレー」に出場
東日本大震災の影響は受けなかったものの、
緊急時への備えは常に必要
緊急時への備えは常に必要
東日本大震災が発生したときは中学校1年生で、宮城県内の自宅にいました。薬剤がなかなか入手できなかった方もいると聞いていますが、僕はたまたま1か月分の薬剤を処方してもらった直後で、家の被害などもなかったので、影響は受けませんでした。震災の際には特に、医療機関の皆さんが最優先でサポートしてくださって、何事もなく過ごすことができました。深く感謝しています。
震災のときの話ではありませんが、「薬剤のストックはあったものの、使える状態の投与用のキットが手元になくて困った」という話を患者会の方から聞いたことがあります。災害に限らず、例えば旅行中でかかりつけの病院に行けない、主治医とすぐには連絡がとれないということもあり得ます。キットの組み立てに失敗してしまうこともあります 。何をどの程度用意しておいたらいいのか、予め医療関係者の方と相談しておいた方がいいと思います。
震災のときの話ではありませんが、「薬剤のストックはあったものの、使える状態の投与用のキットが手元になくて困った」という話を患者会の方から聞いたことがあります。災害に限らず、例えば旅行中でかかりつけの病院に行けない、主治医とすぐには連絡がとれないということもあり得ます。キットの組み立てに失敗してしまうこともあります 。何をどの程度用意しておいたらいいのか、予め医療関係者の方と相談しておいた方がいいと思います。
できるかできないかは、
やってみなくてはわからない。
ただし、やりたいのであれば十分な知識と準備を
やってみなくてはわからない。
ただし、やりたいのであれば十分な知識と準備を
スポーツなどいろいろなことをしてきましたが、挑戦だったと特に思うのは中学校の部活の剣道、そして現在も続けているキックボクシングでしょうか。
何でもやってみることが大切だと、僕は思います。家でやることが好きならもちろんそれもいいですし、体を動かしたいと思っているのにそれを抑え込んでやらないまま生活するのはもったいない、と。
けがは、自分の体で経験し、勉強することにつながります。自分の体に目を向ければ、痛みやちょっとした体の違和感に気づいて対処できるようになります。そのようにしていくうちに、自分の可能性が見つかります。
同じ血友病といっても、一人ひとり違います。最終的には「やってみた結果、自分はこれができたから続けた」ということになるのですから、当事者が自分自身で経験し、理解するために、まずはやってみることから始まるのではないでしょうか。
小学校を卒業する頃までは僕が運動することに反対していた母も、今は「無理に抑えつけなくてよかった。自分でけがをして、自分で処置したり、できることとできないことを判断したりする能力が身についた。関節症の危険もあって、すれすれだったとは思うけど」と言っています。
ただ、運動をするのであれば十分なケアや準備は重要です。具体的にはストレッチや筋トレ、そして疾患について知ることですね。そして先ほどお話しした薬剤を定期投与する曜日と一番凝固因子活性が低くなる日、あるいは体の違和感といった「危険察知能力」も大切で、これは経験と知識によって身につけるしかないと思います。もちろん先生との相談も必要ですね。
何でもやってみることが大切だと、僕は思います。家でやることが好きならもちろんそれもいいですし、体を動かしたいと思っているのにそれを抑え込んでやらないまま生活するのはもったいない、と。
けがは、自分の体で経験し、勉強することにつながります。自分の体に目を向ければ、痛みやちょっとした体の違和感に気づいて対処できるようになります。そのようにしていくうちに、自分の可能性が見つかります。
同じ血友病といっても、一人ひとり違います。最終的には「やってみた結果、自分はこれができたから続けた」ということになるのですから、当事者が自分自身で経験し、理解するために、まずはやってみることから始まるのではないでしょうか。
小学校を卒業する頃までは僕が運動することに反対していた母も、今は「無理に抑えつけなくてよかった。自分でけがをして、自分で処置したり、できることとできないことを判断したりする能力が身についた。関節症の危険もあって、すれすれだったとは思うけど」と言っています。
ただ、運動をするのであれば十分なケアや準備は重要です。具体的にはストレッチや筋トレ、そして疾患について知ることですね。そして先ほどお話しした薬剤を定期投与する曜日と一番凝固因子活性が低くなる日、あるいは体の違和感といった「危険察知能力」も大切で、これは経験と知識によって身につけるしかないと思います。もちろん先生との相談も必要ですね。

ダイエットの一環として始めたキックボクシング。
今もジムに通っています。
滑り止めと足首の保護のために、
サポーターを両足に着けてトレーニングしています
今もジムに通っています。
滑り止めと足首の保護のために、
サポーターを両足に着けてトレーニングしています
やりたいことはたくさんある。
患者会の活動にもこれから取り組みたい
患者会の活動にもこれから取り組みたい
やりたいことは、まだまだたくさんあります。仕事が落ち着いて気持ちにゆとりが出てきた2023年に、子どもの頃に少しだけ参加したことのある患者会に、父に促されて久しぶりに参加しました。
参加して、不安や悩みを抱えている人が多いことに衝撃を受けました。自分がやってきたことを話したところ、それを聞いて泣いている血友病患者のお母さんもいました。また、自分と同世代、あるいは自分より若い世代で、未来へのビジョンを持ちながら患者会に参加し、活動している人たちがいることを知って、「これは自分も勉強しなくては」と火がつきました。
いろんな方の話を聞き、自分の話もしていきたいですね。僕をこれまで救ってくれた方々に恩返ししたい気持ちもありますし、患者会を「困ったら聞きに行ける場所」という存在にしていきたいと思っています。さらに、血友病について多くの方に知っていただくにはどうすればいいかも考えているところです。
参加して、不安や悩みを抱えている人が多いことに衝撃を受けました。自分がやってきたことを話したところ、それを聞いて泣いている血友病患者のお母さんもいました。また、自分と同世代、あるいは自分より若い世代で、未来へのビジョンを持ちながら患者会に参加し、活動している人たちがいることを知って、「これは自分も勉強しなくては」と火がつきました。
いろんな方の話を聞き、自分の話もしていきたいですね。僕をこれまで救ってくれた方々に恩返ししたい気持ちもありますし、患者会を「困ったら聞きに行ける場所」という存在にしていきたいと思っています。さらに、血友病について多くの方に知っていただくにはどうすればいいかも考えているところです。

たくさんある「やりたいことリスト」の中から、
2023年にはハーフマラソンに挑戦し完走
2023年にはハーフマラソンに挑戦し完走
取材後記
桜井さんはインタビュー終了後、「この近くに、僕が設計した鉄骨を使っている超高層ビルの建築現場があるので、見てきます。明日はキャンプをする予定なのですが、天気が心配ですね」とにこやかに話しながら会場を後にしました。その様子から、日頃からアクティブに動き回っていることがうかがえました。数々のお話をありがとうございました。
他のインタビューを読む